講義とフィールド調査で課題を分析・解決する基本的能力を、産学連携事業で実社会に通用する提案力を身につける。
≪今回お話を伺った方≫

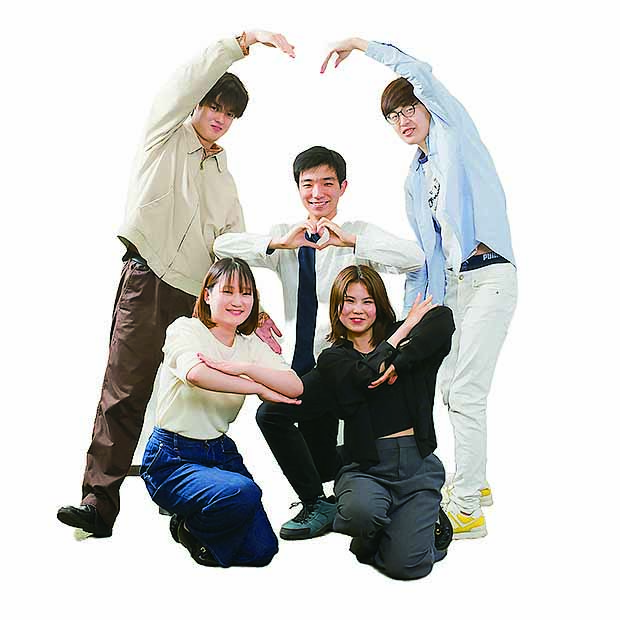
※学生の年次は取材時のものです。
学びの目的を明確に持ち自主的に問題解決を図る
現代の社会に適合的な人材マネジメントについて、座学やフィールドワーク、産学連携事業によって理解を深める柴田好則ゼミ。1年次に柴田准教授の講義を受けた梶原さんは、「もっと学びたい!という気持ちにさせてくれました。人を動かす戦略やノウハウは将来きっと役立つはず」と思い、ゼミの受講を希望したそう。
まずは専門的な知識や理論を身につけ、それらを用いて社会経済における課題を分析・解析し、自立的に問題解決できる能力を身につけることが目標。柴田准教授は学生が自らの足を使って生のデータを収集し、現場のリアルな感情や課題を実感してもらうことを意識しているという。「個々の能力を引き出して利益を生み出す仕組みが人材マネジメント。人をどこでどのように活かすかを判断するために必須である”周りを見る能力”を身につけたい」と中塚さん。奥川さんは「普通の会話は苦手ではないけれど、その人のモチベーションを上げるようなコミュニケーションは苦手。組織や集団において、誰もがやりがいをもって物事に取り組める指示の出し方や、組織のつくり方など、実体験を通じて学ぶために志望しました」と話す。
現場のリアルを実感し実効性のある提案を行う
学生の主体性・自律性を重んじている柴田准教授。「多様な人々との関わりのなかで失敗したり、恥をかいたりしながら、社会に通用する能力を養ってほしい」と考えている。だからこそ産学連携事業において、柴田准教授は採用レベルに達していないと判断した場合、締切の数日前でも修正を求めることがあるという。学生たちは実社会さながらの厳しさを感じつつも乗り越えようと、常に前向きだ。その甲斐あって連携先の企業からは「若者らしい斬新な発想」「発表が上手で、対応が細やか」など高く評価されている。人材マネジメントに興味を抱く泉本さんは「先生の言う通りではなく、自主的に解決策を探し出すことに面白さとやりがいを感じられます」、また冨永さんは「様々な視点から仮説を立てて検証することで、錯綜する世の中に答えを見出すという貴重な経験ができます」と、柴田ゼミの魅力について語る。
今年度は人事・労務で起きているハラスメントやリスキリング、早期離職などの諸問題とその解決について、アカデミックな研究とフィールド調査を通じて明らかにすることを目指しているという。また9月には、国際的な視点を身につけ、より視野を広げることを目的に台湾研修も予定されている。柴田准教授は「好奇心を糧に、失敗や挫折にも負けないレジリエンスを持った自立的な社会人になってもらいたい」と望んでいる。
私たちが柴田ゼミを大好きな理由
(1)自分たちにやる気さえあれば、何にでも挑戦できる場を与えてくれます。
(2)閉店30分前でも懇親会に駆けつけてくれ、みんなの相談に乗ってくれる。
柴田准教授から学生たちへのメッセージ
これからの社会を生きていく上では、どんな困難にぶつかっても、臨機応変に次の道を見つけ、その時々で最善の選択ができる力を求められます。「こうあるべき」という自らのステレオタイプを捨て、皆さんの選んだ道を歩んでください!


この記事は松山大学学園報「CREATION」NO.222でご覧いただけます。





















