≪今回お話を伺った方≫
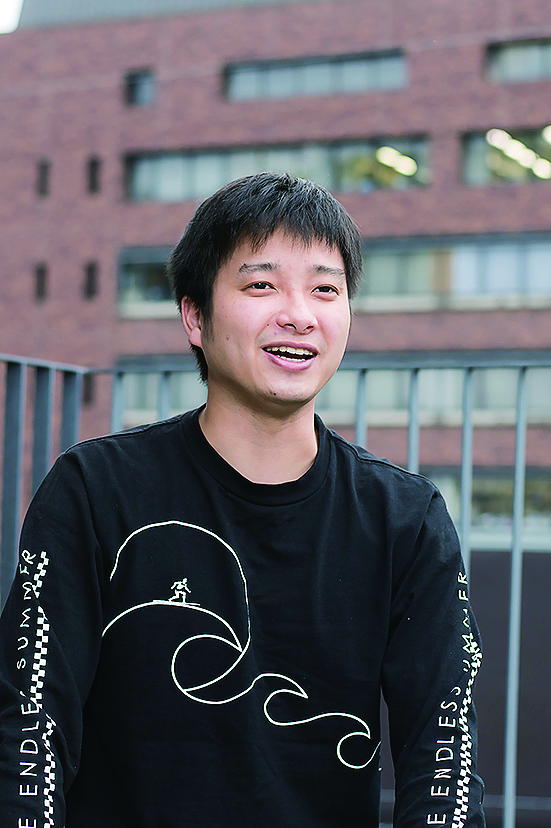


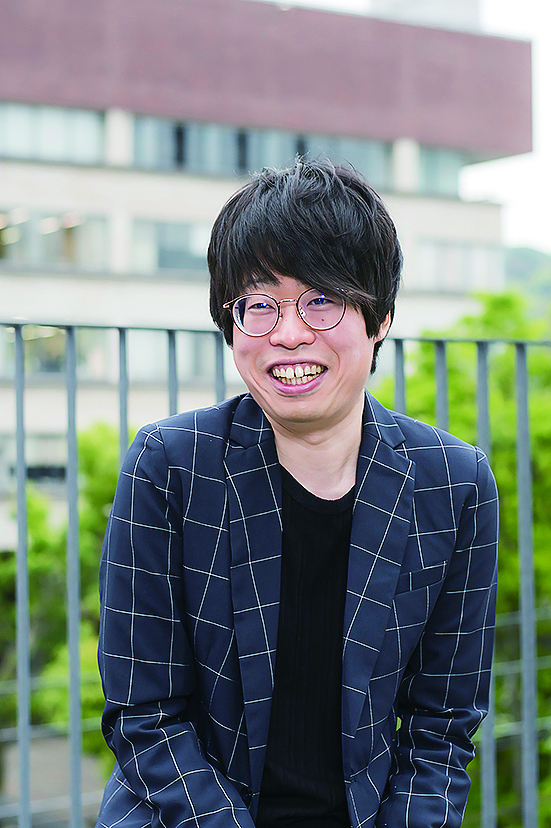
経済学部経済学科准教授 上品 満 UESHINA Mitsuru(写真右)
4年次生 遠藤 滉大さん ENDO Koudai(写真右から2番目)
4年次生 細田 一成さん HOSODA Issei(写真左から2番目)
4年次生 久保 由羽さん KUBO Yuu(写真左)
※年次等は取材当時のものです。
自分で目標を設定し 楽しく取り組めるように
マクロ経済学を専門とする上品満准教授。講義では数式やグラフなどの数学的な話を多く扱うため、資料作成や説明を工夫することにより、学生たちが直感的に理解できるように努めているという。「人にわかりやすく伝える」ことはゼミナール活動においても重視。学生主体のグループワークをメインに、研究とプレゼンテーションの手法を学んでいく。
まず2年次はグループディスカッションやテキストの輪読、経済・社会に関連する時事的なテーマを決めてグループ報告を行う。3年次のゼミナール大会を見据え、互いに議論する力を身につけ、自分で調べた内容を相手に伝える練習をすることが目的だ。ゼミナール大会で発表する研究は、テーマ選びから論文執筆までグループ単位で取り組む。テーマの選定は基本的に学生の自主性を尊重しており、「自分たちが知りたいこと、面白いと思えることが一番。興味のあることなら思考も広がりますし、何より楽しく取り組めると思うのです」と上品准教授。また意欲的に取り組むための一つの工夫として、上品ゼミでは他大学との合同ゼミを実施。今年度は遠隔会議ツールを駆使することにより、広島経済大学との合同ゼミを予定している。
ゼミで培った経験を社会で生きる糧に
昨年のゼミナール大会では参加した3班すべてが受賞するなど、毎年好成績を収めているが、「勝因は上品先生」と遠藤さん。「壁にぶつかったときなど、上品先生が親身になって相談に乗ってくださいました。ゼミナール大会を通じて発言力や傾聴力を身につけることができたので、社会生活に生かしていきたい」と話してくれた。
ゼミナール大会で受賞するという目標をグループで共有し、一人ひとりが役割を持って研究活動を進めていく。「もっとも大切なのは研究の過程であり、受賞の有無に関わらず、研究活動を通じて自分なりの学びがあれば、ゼミ活動に取り組んだ意義は非常に大きいと思います」という上品准教授の言葉を体現するように、4年次生の3人もそれぞれに成長を感じているようだ。人前で発言することが苦手だったという細田さんは「自分からメンバーに積極的に話しかけたり、周囲の意見に耳を傾けたりすることで様々な課題を乗り越え、いつの間にかコミュニケーションをとることが好きになっていました」。また久保さんも「ゼミナール大会では相手の立場となり、わかりやすく質の良い論文をつくることに注力しました。独りよがりにならず、周囲と助け合える社会人になりたい」と話す。上品准教授のもとで学びを深めた学生は、明確な目標を持ち、意欲的に社会を見据えている。
私たちが溝渕ゼミを大好きな理由
先生と学生の距離感が近い!
(1)とてもやさしく気さくな先生で、世間話や悩みも親身に聞いてくださいます。
(2)プレゼン後などにご褒美スイーツあり! 先生が出張に行った際にはお土産も(笑)。


この記事は松山大学学園報「CREATION」NO.210でご覧いただけます。





















