英語力、文化的理解、共同学習スキルの向上を目的とするLANDERゼミ。
学生主体のアクティブラーニングが全編英語の卒業論文への挑戦につながっていく。
≪今回お話を伺った方≫
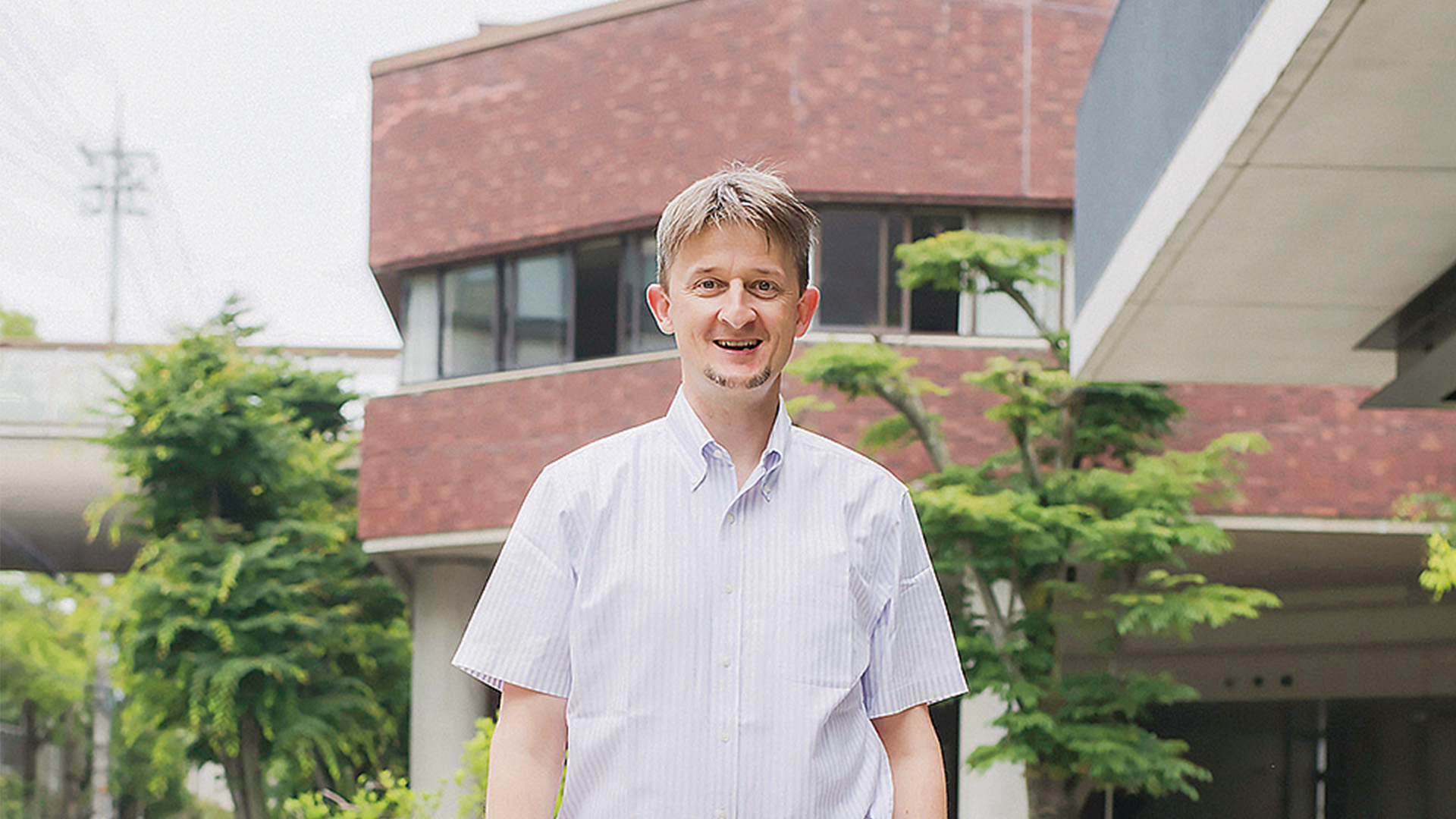




授業は常にキャッチボール
楽しみながら学びを深める
スコットランド出身のブルース・ランダー教授のゼミでは、日本とイギリスの文化や社会の違いを学ぶことをメインテーマとしている。「他国の文化を学ぶことは、実は自国の文化を学ぶことにつながります」とランダー教授。
ランダーゼミは、学生を主体としたグループワークやプレゼン形式での発表などを積極的に行い、学生たちは自身の英語力や文化的理解に加え、共同学習のスキルも高めていく。共同学習には、iPad、パソコン、スマートフォンなどのICT(情報通信技術)を活用。英語力のみならず、共同学習のスキル、デジタルリテラシーなどの向上も意図している。櫛部さんは「授業では毎回スマホやパソコンなどを使うので、自然とデジタルスキルが向上したと思います」と話す。
3年次では文化の違いに焦点を当て、イギリスの社会問題、福祉、教育、政治、ポップカルチャー、観光などのトピックを紹介。学生はまず2〜3人でグループワークを行い、さらにクラス全体に向けて自分たちの考えを発表する。この共同学習においては、Kahoot!(カフート)というインタラクティブ(対話式)のクイズソフトを採用。各プレゼンテーションの最後に、Kahoot!で簡単なクイズを出題することで楽しく教育的な雰囲気をつくり、理解度を高めている。「単にイギリスの文化を学びたいとの思いからブルースゼミを希望しましたが、語学学習の面においても、異文化理解がとても重要であることを、実感しています」と話すのは轟さん。
教育に対するアプローチをよりアカデミックに
4年次では「教育論・教育哲学」をテーマに、ルソー、デューイ、ロック、モンテッソーリなど、教育哲学に影響を与えた人物について議論を交わす。そのため、伊藤さんや加地さんのように教員を目指す学生も多い。教育について、英語で勉強したいと思っていたという伊藤さんは、ゼミでの学びを通して「ランダー先生は、学生が書いたレポートやサマリーを細かいところまで指導してくださったり、ネイティブスピーカーの感覚でライティングする際のルールなどを教えてくださったり。そのおかげで、英語の4技能のなかでも、特にライティング技能が向上したように思います」。
そして英語で卒業論文を書くという集大成に向けても、着実にスキルを伸ばしている。ランダー教授も「本講義での教育論・教育哲学をはじめとする様々な学問領域についての学びを、今後の活動の指針としてほしい」と期待を寄せる。
私たちがLANDERゼミを大好きな理由
(1)授業は「聞く」というより「コミュニケーション」。気軽に発言しやすい環境です。
(2)課題ごとに評価やコメントがもらえるので自分の成長を感じることができます!


この記事は松山大学学園報「CREATION」NO.214でご覧いただけます。





















