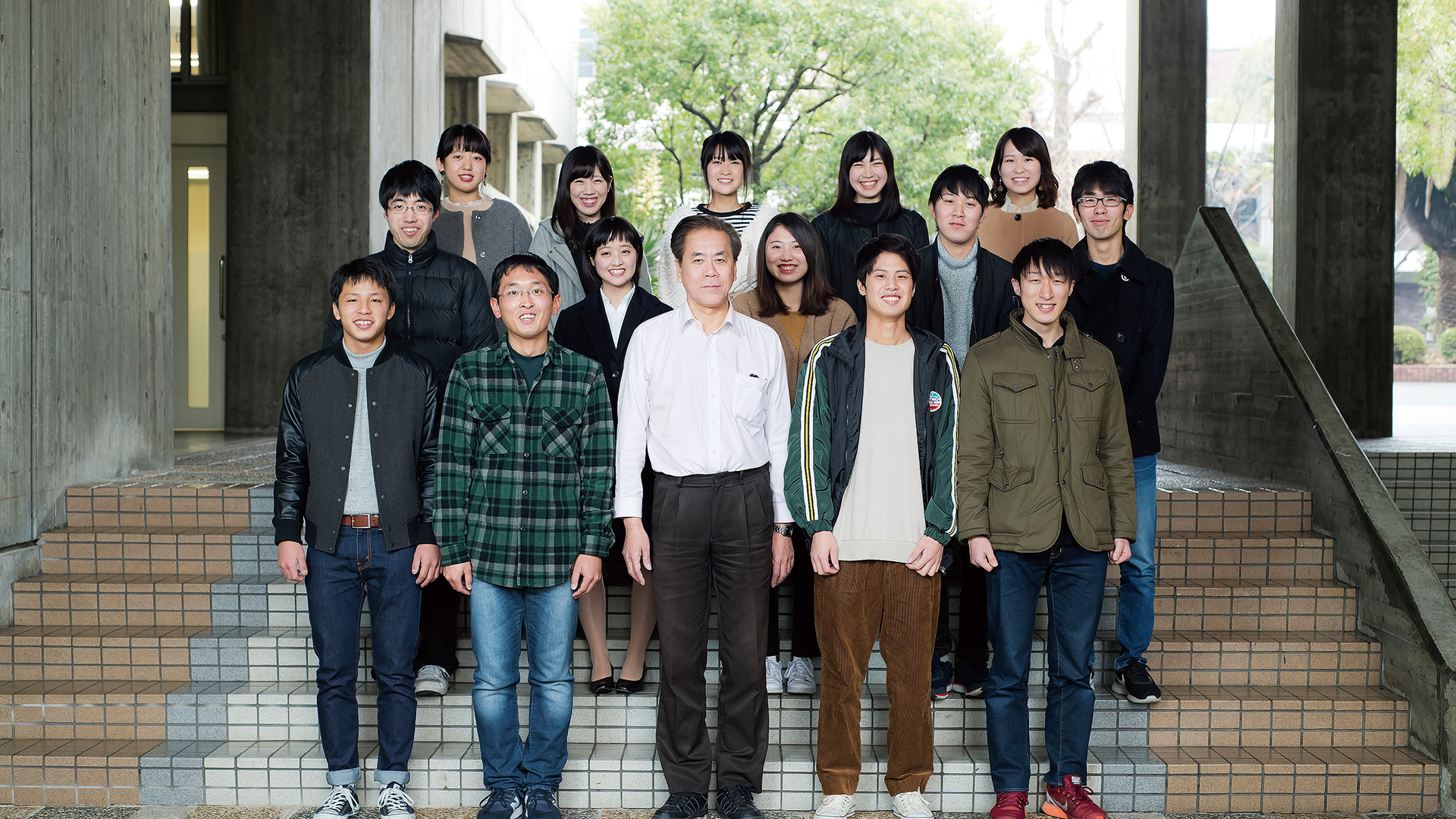≪今回お話を伺った方≫



人文学部社会学科教授 市川 正彦 ICHIKAWA Masahiko(写真左)
4年次生 宇和川 佳那さん UWAGAWA Kana(写真中央)
3年次生 渡邊 奈菜さん WATANABE Nana(写真右)
※年次等は取材当時のものです。
社会や行政に関心を持ち探究心を持って調査
過疎化・高齢化の進行が顕著な四国は、解決すべき地域問題が山積みの状態といえるのではないだろうか。東京出身の市川教授は、松山へ移り20数年。地域社会学を専門分野とし、地方都市の調査研究に力を入れている。
ゼミのテーマは、地域社会の研究。毎年、愛媛県内の一つの自治体を対象に質問紙調査を行い、データを分析し報告書を作成。自治体の抱える問題点について、住民の意識調査の集計結果をもとに考察していく。
まず2年次では地域問題を扱った文献を学び、調査地となる自治体を調べる。行政・合併・産業・まちづくりなどのテーマを2〜3名ずつのグループに分かれて資料収集と分析。3年次になると、いよいよフィールドでの地域調査が始まる。各グループで調べたことを元に仮説を立て、それに基づいた質問を集約し「調査票」を作成。市役所や役場で調査対象となる住民を自分たちで無作為抽出し、対象者に調査票を郵送する。そして得られた回答をまとめ、統計ソフトを用いて集計し、分析を行う。
サンプリング(標本抽出)の仕方、調査票の発送業務、データ入力の仕方、統計ソフトの操作法などは、地域調査を行う市川ゼミならではの学びでもある。「地方公務員を目指しているので、地域社会の研究に興味を持ちました。先生のもとで学んだ調査ノウハウは社会人になったとき、強みになると思います」と3年次生の渡邊さん。「彼女のように公務員となって地域に貢献したいという希望を持っている学生もいますね。うちのゼミを希望するのは、多少なりとも地域問題への興味を持った学生が多いようです」と市川教授も続ける。
自分なりの視点で分析、主体的な取り組みを評価
4年次では個人で卒業論文に取り組むことになるが、市川ゼミでは、質問紙調査やインタビュー調査を行い、オリジナルのデータで卒論を制作する学生が増えているという。「ただ文献を引用するだけではなく、実際に自分でデータをとり、それを自分なりの視点で分析するなど主体的に取り組む学生の姿を見ると、3年次のゼミがある程度は活きているかなと感じます」と市川教授も目を細める。4年次生の宇和川さんは、この春から地元広告業への就職が内定。「ゼミ活動を通じて、もっと地域を知ろうという意識が芽生えました。今後は社会人として、地域の人々にしっかり響く広告をつくることができたらと考えています」と目を輝かせる。
「理想を言えば、自分のゼミの卒業生から市長や市議が生まれ、地域活性化を担ってもらえたら」と市川教授。地域に根ざした大学から、地域を担う人材を輩出する。地域社会や行政に関心を持つことが、そんな未来への第一歩となるだろう。
私たちが市川ゼミを大好きな理由
みんなが自然体でいられる居心地のいい場所です!
(1)ちょっとユニークな先生、よく笑う仲間、程よい個性や自己主張、のんびりした雰囲気。全部最高!
(2)先生はまるで歩く図書館!学術から雑学、グルメまで、聞いたら何でも教えてくださいます。