≪今回お話を伺った方≫


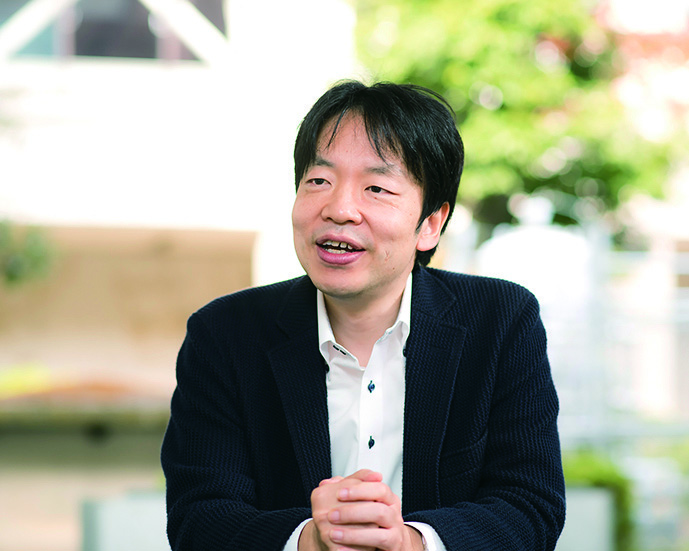
人文学部社会学科教授 大倉 祐二 OHKURA Yuji(写真右)
3年次生 土井 美月さん DOI Mizuki(写真中央)
3年次生 村上 紗耶さん MURAKAMI Saya(写真左)
※学生の年次は取材時のものです。
身近な問題を社会的に考える思考を養う
「とにかくやさしくて、何でも相談できる」と学生からの信頼も厚い大倉祐二教授。その人柄に惹かれて大倉ゼミを志望する学生も多い。専門分野は「貧困」。ゼミでは、まず2年次にホームレス問題について学び、3年次は1年かけてグループで論文を書くことを目標としている。「扱う題材が社会問題やホームレス問題であり、その問題の渦中にいて困難に直面している人たちの暮らしを知ることで、他者に対するやさしさを学生にはもってほしい」と大倉祐二教授。「それまでホームレスは別世界のことに感じていましたが、大倉ゼミでの学びをきっかけに、より身近な問題として捉えられるようになりました」と村上紗耶さんが話すように、大切なのは、自分に引き付けて物事を考えること。具体的な社会問題を考察、分析することで、社会問題に対する人々の認識と実態とは、必ずしも一致しないことを知ることがゼミのテーマだ。
今年度の3年次生のグループワークは、LGBTや若者の貧困などがテーマとして挙がっている。「LGBTの人が抱える雇用問題」をテーマに取り組む土井美月さんは「この分野はまだ解決されていない部分も多いため、これからの社会を担っていく私たちが考え、取り組んでいかなくてはいけない問題」だと話す。「狭いテーマで濃密な内容を書いた方が研究性の増したレポートになる」と大倉祐二教授からアドバイスを受けたことで「具体的に、より深く掘り下げることができた」と手応えをにじませる。
「学生には、主体的に楽しく学んでほしい。教えられるだけでは受け身になってしまい、それ以上の発見はないと思っています。学生たちのやる気を引き出し、困ったときにはいつでも相談に乗れるような存在でありたい」。そんな大倉祐二教授の期待に応え、ゼミ生は積極的に意見を交わし、学びを深めている。
他者に対するやさしさをもち、社会へと羽ばたいていく
現在3年次生の二人は、就職活動の真っ只中でもある。「大倉先生から教えていただいた『他者を思いやる気持ち』を軸として、地元に貢献したい」と村上さん。土井さんも「子どもが好きなので、その成長過程を支えてあげられるような仕事ができたら。間接的でも子どもたちのために何かできないかと、見方を変えて考えられるようになったのは先生のおかげです」と話す。「社会生活は、他者といかにうまくやっていくか。協力することで結果が出てくると思いますから、独りよがりにならず、相手をよく見て対応できる人になってほしいですね」。そんな大倉祐二教授の想いに「まかせてください」と二人。他者へのやさしさをもち、大倉ゼミの学生たちは社会へと羽ばたいていくことだろう。
私たちが大倉ゼミを大好きな理由
大倉先生がやさしく、何でも相談できる!
(1)やさしくてノリがよく、学生目線で考えてくださる先生なので、何でも相談できます。
(2)クリスマスらしいことをしたいと言ったら、ケーキを用意してくれて感動!


この記事は松山大学学園報「CREATION」NO.208でご覧いただけます。





















