≪今回お話を伺った方≫


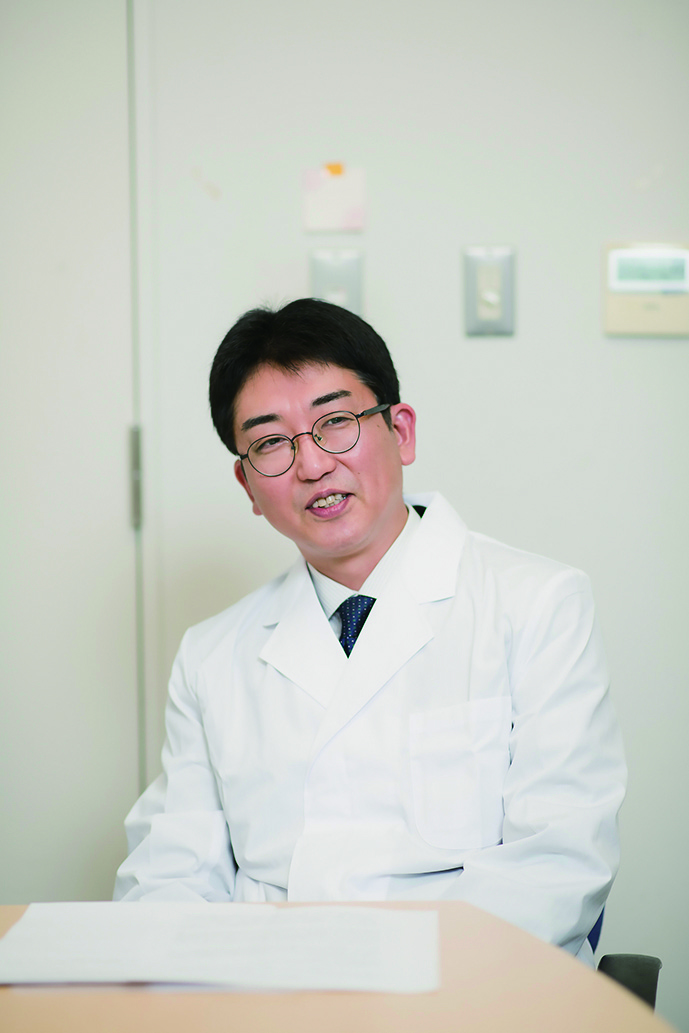
薬学部医療薬学科教授 舟橋 達也 FUNAHASHI Tatsuya(写真右)
5年次生 赤松 祐花さん AKAMATSU Yuuka(写真中央)
5年次生 池田 凌さん IKEDA Ryo(写真左)
※学生の年次は取材時のものです。
研究活動を通じて問題解決能力を養う
薬学部の学生は、入学後3年間の基礎学習を経て、4年次生より研究室に配属。それぞれの研究室で実験研究に取り組み、さらに学びを深め卒業論文発表会、卒業論文作成に向けて研究を行う。
舟橋達也教授が指揮をとる衛生化学研究室の研究テーマは、「食中毒細菌や日和見感染菌における鉄獲得機構について、分子生物学的手法を用いて明らかにする」。ほぼすべての生物に必須であり、細菌の生存・増殖にも必須の元素である鉄。地球上で4番目に多い元素だが、多いからといって容易に取り込めるわけではなく、細菌は鉄を効果的に獲得するために様々な機構を持っている。衛生化学研究室では、細菌における鉄獲得機構の仕組みを明らかにすることで、新たな感染症治療薬のターゲットを提示することができるよう研究を進めている。
鉄獲得機構の研究に取り組む5年次生の赤松祐花さんと池田凌さんは、その過程で舟橋教授からのアドバイスに助けられているという。「実験がなかなかうまくいかないとき、先生は原因がどこにあるのか一緒に考え、解決へ導けるように指導してくださいます」と話す赤松さんに、「研究の成果が直接仕事に役立つということはほとんどないかもしれません。しかし試行錯誤を重ね、思考を繰り返す研究過程で身につけた問題解決のための方法などは、様々な場面で役に立つと思います」と応える舟橋教授。
研究に限らず、あらゆる活動を通して問題解決能力を身につけておくこと、それが今回のコロナ禍のように、すぐに答えが出ない問題に直面した際の対応力にも繋がるのではないか。そう考えるからこそ、舟橋教授は学生たちの自主性を尊重し、個々の適性や関心のある分野を踏まえたサポートに努めている。
学生時代の経験が将来の財産になる
薬学部の数ある研究室のなかで衛生化学研究室を志望した理由として、「細菌を使った研究内容に興味があったのもありますが、一番は、実習や研究室訪問の際の舟橋先生や先輩方の人柄の良さに惹かれたことです」と池田さん。舟橋教授は、研究室内での交流を深めるため、学生間での自主的な勉強会を推奨。学年を超えた学びの場をコーディネートしてきた。
現在はコロナ禍のため難しい状況だが、Zoomによる面談などオンラインツールを活用し、交流の機会を確保している。「研究を通じて、一緒に新しいことを見つけて楽しみたいですね。そして彼らには学生時代の経験を将来の財産にして、様々な場所で活躍する薬剤師になってほしいと思います」。そう語る舟橋教授が学生たちに向けるまなざしは、とてもやさしい。
私たちが衛生化学研究室を大好きな理由
ノリが良くて、みんなやさしい!
(1)研究もイベントごとも、学年を超えて楽しく取り組んでいます。
(2)困ったことがあれば、先生やみんなが必ず一緒に考え、助けてくれます!


この記事は松山大学学園報「CREATION」NO.209でご覧いただけます。





















