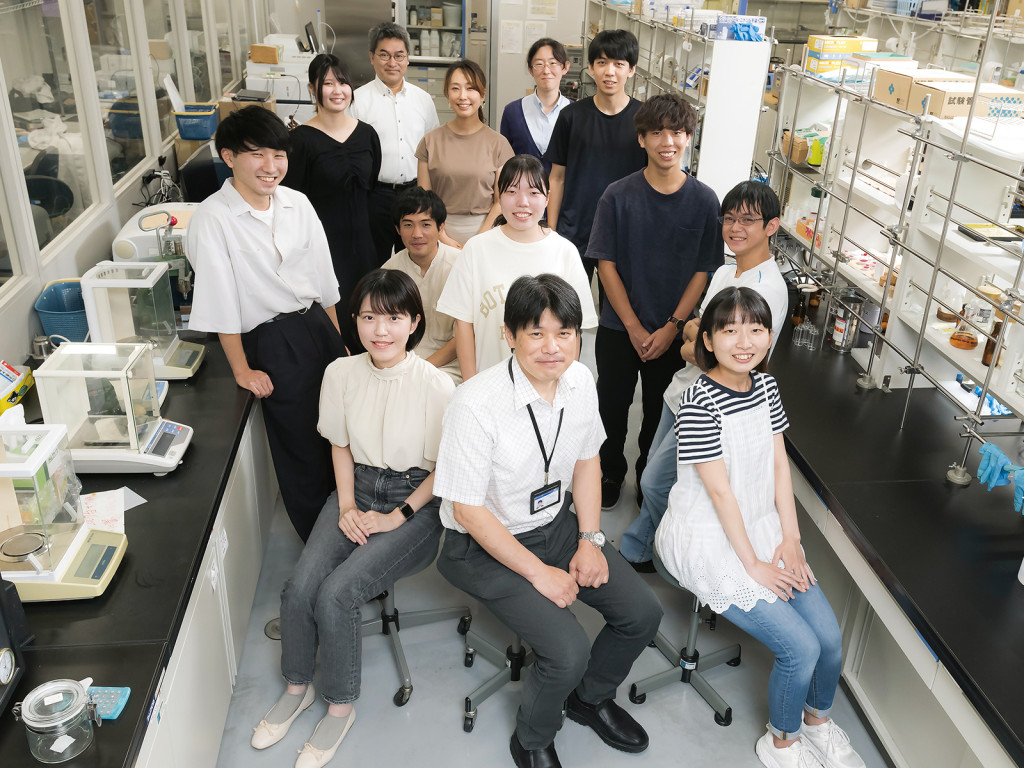医薬品開発に役立つ反応の開発を目的に、新反応の発見に挑む有機化学研究室。
有機化学の研究を通し、常識や固定概念の外を観る力、そして、より広い世界へと突き進む力を培う。
≪今回お話を伺った方≫


※年次等は取材当時のものです。
実験研究+座学=「人生観」
学びを通して「心の目」を養う
「有機化学」とは、炭素を含む有機化合物を研究対象とする化学の一分野だ。医薬品をはじめ工業製品、ペットボトル、ナイロン繊維など、身のまわりの様々なものに有機化合物が使われており、私たちの生活にとても身近な学問といえる。有機化学研究室の今年度のテーマは大きく二つ。まず一つは、医薬品の合成に役立つ反応開発。多くの医薬品に含まれているフッ素原子を、より効率的に導入する反応の開発に挑んでいる。もう一つは、生体現象を明らかとする発光性分子の開発。有機分子の集まりである生体内で何が起こっているのか。シグナル伝達などの生体現象を可視化する、つまり私たちの「目」と
なる発光性分子の開発だ。これらの研究において対象となる有機化合物の仕組みは、目に見えないもの。だからこそ、想像力や思考する力が重要だと北村正典教授は話す。「我々は、注意を向けなければ在る物が視界に入っていたとしても見えません。逆に、注視することによって、実際には目に見えない分子の様子が心の中に広がります。当研究室では、学びを通じて“心の目”を養うことを目標に、日々努力を重ねています」。そのためのファーストステップとして、配属された4年次生は、まず有機化学反応の練習実験を個々に行う。全員同じ内容の実験を行うが、その結果はほとんどが違うものになるという。そこで、皆で話し合い、その原因を手探りで突き止めていく。「自分と仲間の経験を擦り合わせ、原因究明に達したときの一体感はこの上ないものです」と話す。
可能性を広げるのは自分
外を観て、そして外へ進め
有機化学の研究を通して視野が広がった自身の経験から、北村教授は研究室での学びを「人生観」と捉えている。「研究は、これまでの人類の経験の外にあるものを見出すこと。よって、研究を通して自分たちの外にある新しい概念を見出すことを目標としています」。これまでになかったものを生み出す研究は困難も多く、失敗することも少なくない。学生たちからは「そんなとき、先生は『この失敗が新たな発見につながるかもしれない』とポジティブな視点を示してくださりました」「研究を通して常に疑問を持ち、物事の理由を考えるようになりました」という声があがっている。考えることを諦めず、チャレンジを続ける有機化学研究室の学生たち。その積み重ねが、世の中の常識を変える新発見へとつながるかもしれない。
私たちが有機化学研究室を大好きな理由
(1)「自主自律」の精神。学生の意思を尊重し、柔軟な発想で物事を考える力が身につきます。
(2)仲が良く、メンバーの誕生日にはポップコーンでお祝いをしています。
北村教授から学生たちへのメッセージ
薬学部だから医療人、薬剤師ということはなく、可能性は無限大。常に自分の頭で考えて、外に広がろうとする「プロフェッショナル」を目指してほしいと思います。


この記事は松山大学学園報「CREATION」NO.215でご覧いただけます。