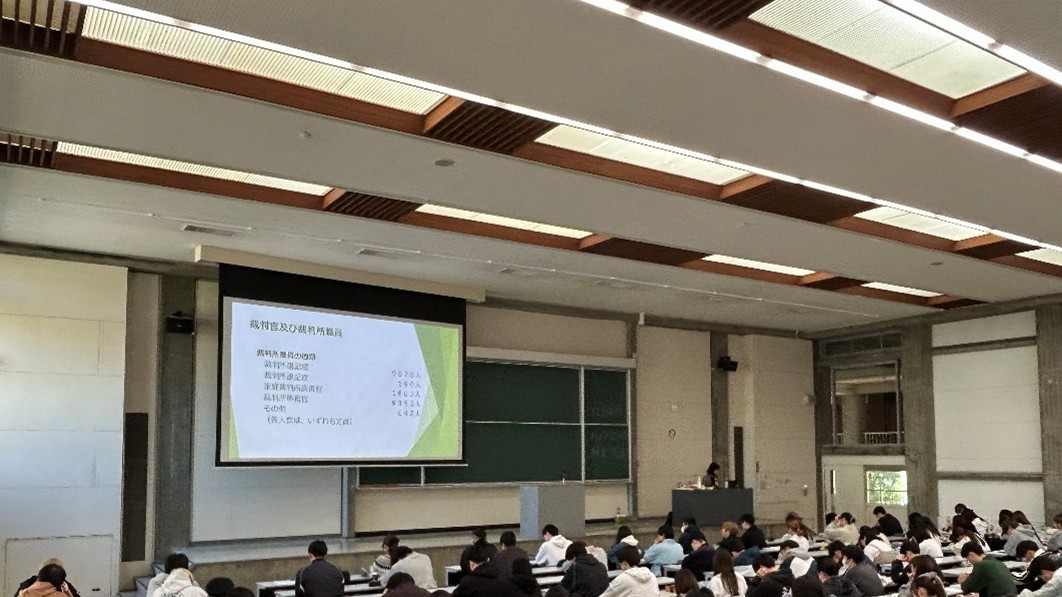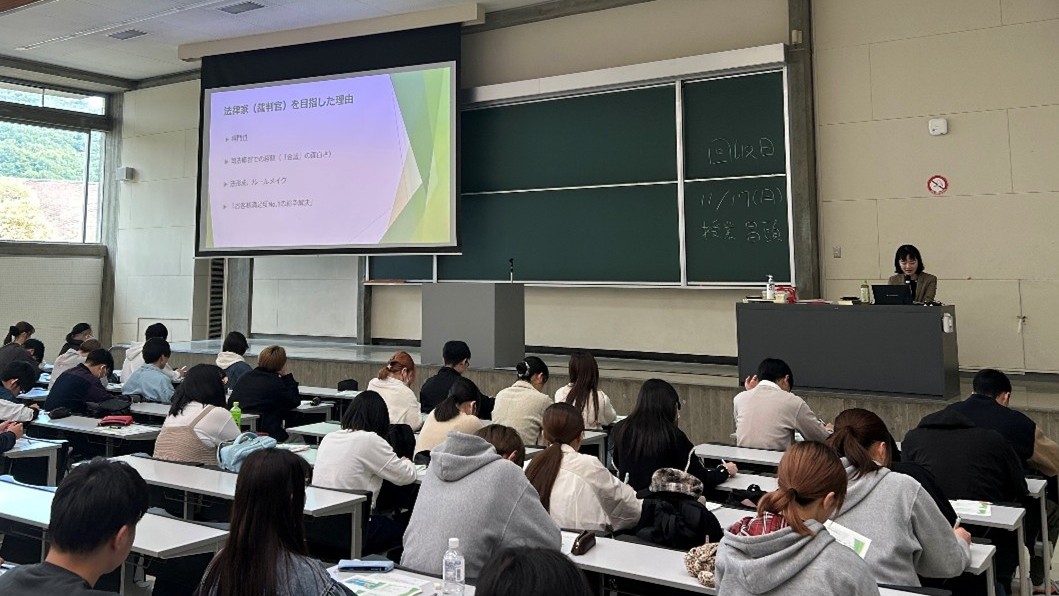2025(令和7)年11月10日(月曜日)、松山大学法学部・講義科目「刑法I(総論)」(刑法総論分野)の一環として、裁判官(松山地方裁判所所属・左陪席)をお招きし、「裁判の実際―刑事裁判を中心に―」をテーマとして講演していただきました(受講人数274名:この企画は、2016(平成28)年度からコロナ期を含め継続して実施しております)。
まず、裁判所の役割に関して三権分立から説き起こし、裁判所の組織・裁判官及び裁判所職員の構成等が解説されました。次に、裁判の構造(三審制:第一審〔地方・家庭裁判所など〕、第二審〔高等裁判所〕、第三審〔最高裁判所〕)・裁判の種類(刑事事件、民事事件〔地方・簡易裁判所〕、家事事件、少年事件〔家庭裁判所〕)に言及があった後、刑事裁判の概要に触れられた後、裁判員裁判に関して解説がありました。裁判員裁判(平成21〔2009〕年から運用開始)について解説がありました。成人年齢の引き下げに伴い、大学1年生からすでに裁判員になる可能性があることに鑑み、「裁判員裁判事件数の推移」(新受件数)(松山地裁 令和5〔2023〕年:10件、令和6〔2024〕年:7件、令和7〔2025〕年:7件〔2025年11月10日現在〕)の他、裁判員裁判において裁判所が注意している事項、すなわち、公判は、「見て、聞いて、分かる」審理が目指され、評議・評決は、裁判員には意見を述べる義務があり、評議の際は「乗り降り自由」であることなどについても情報提供をいただきました。
その後、若手裁判官すなわち左陪席裁判官の業務内容(「刑事部左陪席裁判官の業務内容」及び「民事部左陪席裁判官の業務内容」)について、ご自身の経験も踏まえた1週間の業務内容(典型的な業務内容)をお示しいただきました。
最後に、今後、法曹を目指す学生に対して、具体的な情報をお示しいただきました。
講演会終了後、4名の学生から質問が出され、さらに講演会終了後の個別的な質問についても、時間をかけて対応していただきました。