移動サポート研修会・車いす体験会
7月13日(日曜日)9時から12時30分まで、松山大学にて、自立生活センターCIL星空様ご協力のもと「移動サポート研修会・車いす体験会」を実施しました。
この研修会・体験会は、今年度からPOPで活動を開始した、車いす利用学生へのサポートに必要なスキルや関わり方について学ぶため企画しました。
移動サポート研修会では、CIL星空様の紹介や障がいの社会モデルなどについて教えていただきました。この研修では、「障がい」という言葉について考えさせられました。社会モデルの考え方では、障がいは誰にでも起こり得るもので、環境が変われば私たちも障がい者となることがあるため、障がいを当事者として考えることがとても大事であることがわかりました。
車いす体験会では、2人1組となり、実際に車いすに乗って、松山大学内や近くの駅、コンビニに行きました。初めて車いすを利用したため、車いすを動かすだけでとても疲れました。車いすで移動してみると、少しの坂、でこぼこ、段差でも不便を感じることが多く、大学構内や駅は車いす利用者にとって、まだまだ不便な点が多いことがわかりました。コンビニでは、高い場所にある商品が取れない、通路の幅が狭いなど不便を感じることが多くありました。
今回、「障がい」についての考え方や車いすを利用することの大変さなどを知ることができ、とても良い機会となりました。こうした活動を通して学んだことを、今後、多くの人に伝えていきたいと思いました。
法学部法学科2年次生 藤田小夢


あいサポーター研修
7月5日(土曜日)10時から11時30分まで、松山大学で行われた「あいサポーター研修」にPOPの学生10名が参加しました。
愛媛県障がい者社会参加推進センターが実施している「あいサポーター研修」は、障がいのある方への支援について学び、日常生活のなかで障がいのある方が困っているときなどに、できる範囲でちょっとした手助けをする「あいサポーター」を養成する研修で、愛媛県が実施している「愛顔のあいサポート運動」の一環として行われています。
研修では、障がいにはたくさんの種類があり、見た目でわかるような障がいもあれば、一目見ただけではわからない内面的な障がいも存在していること、周りに理解されにくいことで困難を抱えている方もいることを学びました。
また、段差を解消するためにスロープが設置されていますが、実際に車いすに乗ってスロープを利用すると、角度が急すぎたり、緩やかであっても距離が長すぎたりすると大変であることがわかりました。スロープを設置するという合理的配慮がなされていても、実際に使ってみないとわからない大変さがあると知りました。
障がいと一言で言っても、人によって必要な支援が異なること、配慮を必要とする方とそうでない方がいらっしゃることを知り、まずは一人ひとりに声掛けをしてから対応することが大切だとわかりました。また、支援を行う際には前方から声を掛ける方が望ましいと知り、意識して行動しようと思いました。
今回の研修を終えて、今後はあいサポーターの一員として、自分にできることはないかを意識して行動し、困っている人がいれば声を掛けられる人になりたいと思いました。研修終了後にいただいた“あいサポートバッジ”を、身に着けていきたいと思います。
人文学部社会学科3年次生 片上夏萌
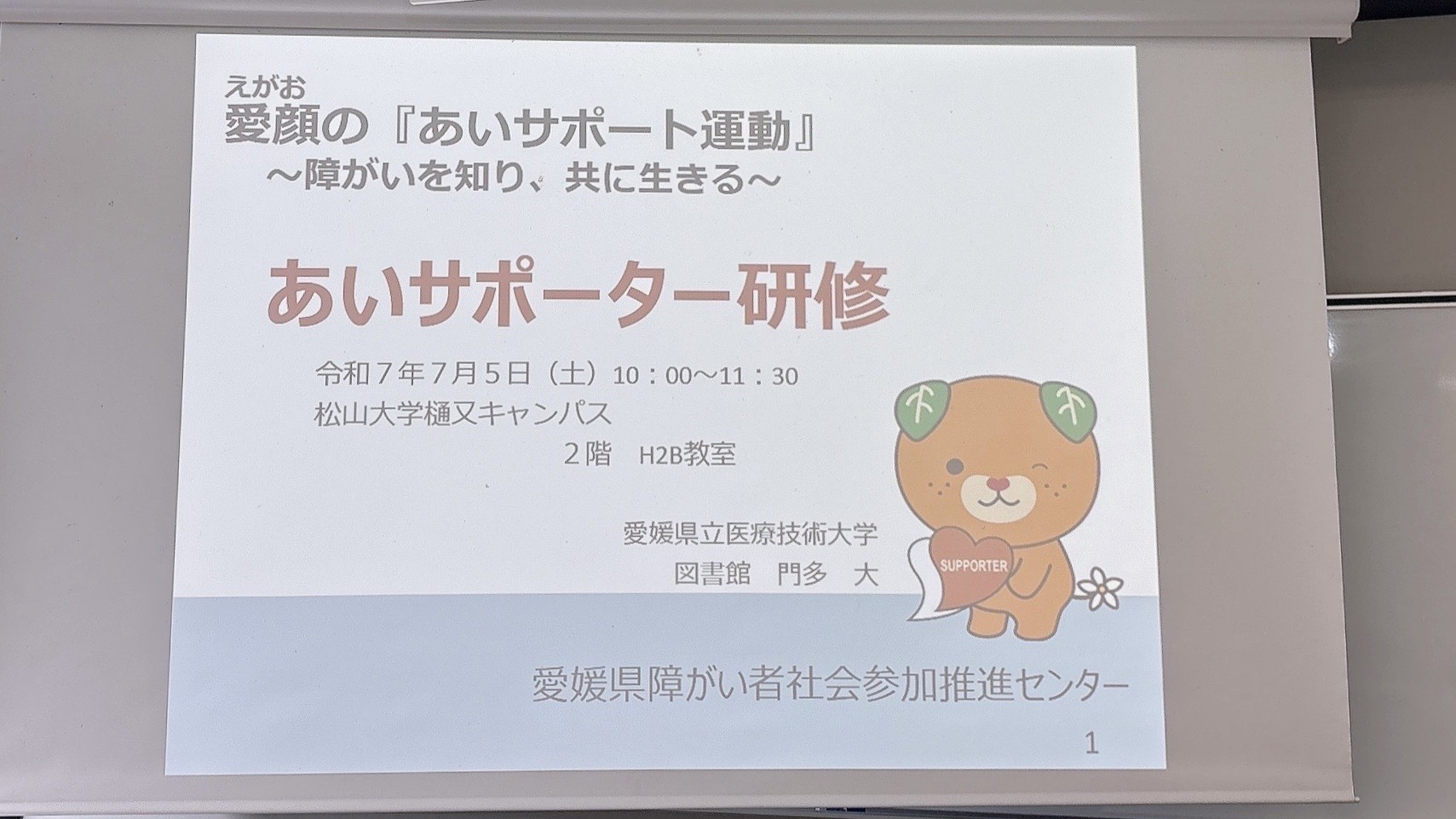

愛媛大学手話サークルとの交流会
6月26日(木曜日)18時から20時まで、愛媛大学で行われた、愛媛大学手話サークル「しゅわくりぃむ」との交流会に参加しました。
はじめに、名前、大学名、学部・学科、出身地、趣味などの自己紹介を手話で行いました。事前に少人数で手話表現を確認してから臨みましたが、愛媛大学の皆さんの流暢な手話に驚き、自分の未熟さを痛感しました。また、わからない手話があればすぐに調べるなど、わからないことをそのままにせずに取り組む姿勢を見て、私も見習いたいと思いました。
次に、3つの単語を使ってお題を伝えるゲームをしました。始める前に言葉の由来とともに手話単語を教えてもらったことで、より理解が深まり、記憶にも残りやすかったです。例えば、「白」の手話は、歯を指でさして左方向に振るという動作をしますが、これは歯が白い様子を表しています。また、ゲーム内では、愛媛大学の方々が指文字を習得し使っていたことにも驚きました。
最後に、ペアになって雑談をしました。POPの3年次生の先輩方は会話と手話を自然に組み合わせてコミュニケーションを取る姿が印象的で、私もそのようなスキルを身につけたいと強く思いました。
今回の交流会は、手話への理解を深めるとともに、今後の日常生活にも積極的に手話を取り入れたいと思える非常に有意義な時間になりました。
法学部法学科2年次生 近藤緋音

視覚障がいを考える勉強会
6月21日(土曜日)16時から18時まで、サイボウズ松山オフィスで開催された「視覚障がいについて考える勉強会」にPOPの学生4名が参加しました。勉強会では、視覚障がいに関わる企業や団体、コミュニティの紹介や取り組みをお伺いしました。技術やデザインの力で、視覚障がいのある方の世界を「楽しく」彩っている皆さんの取り組みは非常に興味深く、聞いているとワクワクしました。
また、POPの活動について紹介する場を設けていただき、多くの方々からお褒めの言葉やアドバイスをいただきました。「分からないことがあれば、まずは我々を頼ってほしい」という心強いお言葉もいただき、これからの活動の励みになりました。障がいのある学生の学生生活がサポートできるよう、これからも活動に取り組んでいきたいと思います。
法学部法学科3年次生 山田悠真

6月オープンキャンパス
6月21日(土曜日)、松山大学で行われたオープンキャンパスにて、ケガや病気・障がい等により配慮が必要な参加者への支援活動に取り組みました。当日の具体的な活動は、車椅子を使用している方に対し、教室の席の確保や案内、キャンパスツアーを行い、安心してオープンキャンパスに参加していただけるようサポートすることでした。
当日までの準備として、席の確保の仕方や当日の流れ等について、メンバー内での話し合いや学生支援課の職員の方との打ち合わせを重ねました。
当日は、急な教室の変更があり、席の確保に戸惑うこともありましたが、対応においては大きな問題もなく、ほとんどの支援を計画通りに進めることができました。
POPとして、オープンキャンパスで配慮が必要な方への支援を行うことは初めての試みであったため、支援の方法や当日の計画の立て方など、手探りのところがあり、至らない点もあったと思いますが、やり遂げることができてよかったです。改善点はありますが、この経験を今後のオープンキャンパスでの支援に役立てていきたいです。そして、支援を必要とする方が、安心してオープンキャンパスに参加でき、松山大学の特色や魅力を知ってもらえる機会となるように、活動していきたいと思います。
法学部法学科2年次生 若江真優


松山盲学校授業参観
6月11日(水曜日)と13日(金曜日)の2日間、愛媛県立松山盲学校の授業参観に参加しました。POPのメンバーは、計10名が4つのグループに分かれて参加しました。
私たちは13日(金曜日)に訪問し、色彩の感じ方や、視界がぼやけたりまぶしく見えたりする見え方を体験できるアプリを使わせていただきました。そこで、校長先生から、「目が見えにくいから席を前の方にしてあげる、明るい席にしてあげる、などの一律の対応ではだめで、視野が狭い人は、反対に席を遠くする必要があり、明るく見える人は暗い所に席を配置したりカーテン閉めてあげたりする必要がある」というお話を聞きました。その人に合った対応をしなければ独りよがりの対応になるというお話は、大変勉強になりました。また、弱視は9歳までに矯正すれば治るため、早期発見が大事だという話にはとても驚きました。
さらに、サウンドテーブルテニスやバレーボールなど、音を頼りに行うスポーツがあることを知りました。実際の動画を見せていただきましたが、とても難しそうでした。
図書館に行った際、点字の本や新聞を初めて目にし、非常に興味を持ちました。その中には、点字の三国志もありました。また、点字を打つ体験をさせていただきましたが、真っ直ぐ打つのが難しかったです。早打ちで6点全てを打つというものがあり、早い人は2分で90個打てるという話を聞いて驚きました。
今回、松山盲学校の授業参観に参加したり、校長先生のお話をお伺いしたりしたことは、とても有意義で貴重な機会となりました。
人文学部社会学科2年次生 野村帆乃
人文学部社会学科2年次生 百田愛優
松山盲学校運動会見学
5月24日(土曜日)、愛媛県立松山盲学校で開催された運動会をPOPの学生2名が見学しました。当日はあいにくの雨となり、体育館での開催となりましたが、保護者や地域の方々が多数来場され、温かい雰囲気に包まれていました。
実際に運動会を見学し、教職員と生徒の距離の近さに驚きました。また、保護者や卒業生の方々も一体となって運動会を盛り上げており、学校全体が活気に溢れていました。盲学校ならではの競技が多く、観戦するだけでも非常に楽しむことができました。
競技には音を活用した種目が多くありました。“ナイスキャッチ”という種目は、ボールの中に入っている音を聞き、転がっている短い時間の中で場所を把握しキャッチする競技で、転がっている音を聞くために、静かにしなければなりませんでした。キャッチした時の嬉しさ、驚きをたくさんの方と共有でき、一緒に楽しむことができました。教職員の方々も積極的に競技へ参加しており、その姿にも大変驚きました。
運動会を通して特に印象深かったのは、音声情報の工夫です。すべての競技に実況が付き、視覚に障がいのある人でも、あたかも見えているかのように競技を楽しめるようになっていました。子どもたちが大きな声で仲間を応援する姿を見て、目が見えなくても音や声を聞いて楽しんでいることが伝わりました。
このような経験を通して、音声情報の重要性だけでなく、学校・家庭・地域が一体となって子どもたちを支えることの大切さを実感しました。今後も、松山盲学校の文化祭や授業公開などに参加したいと思います。
人文学部社会学科2年次生 清水理子
新歓イベント
4月22日(火曜日)、843教室で新歓イベントを行いました。POPの普段の活動を紹介したり、手話チームと情報保障チームに分かれてゲーム形式の企画を実施したりするなど、新入生にも楽しんでもらえるよう工夫しました。ゲームでは、手話チームが「はあっていうゲーム(手話版)」を、情報保障チームが「タイピングの伝言ゲーム」を行いました。
2か月前から準備を進め、どのような内容なら新入生に活動の魅力が伝わり、かつ楽しんでもらえるのかを各チームや全体で話し合いながら企画を考えました。2年次生が主体で新歓イベントを運営しましたが、初めての経験だったため、みんなでアイデア出し合い、スライドにまとめていく作業は想像以上に大変でした。ですが、この経験が、協力しながら物事を進めていくことの大切を実感するきっかけとなりました。
当日は、先輩方にサポートしていただきながら、初対面同士でも楽しく活動でき、またPOPの普段の活動をしっかりPRすることができたことに達成感を感じました。
今後は、2年次生が任される仕事も増えてくると思うので、今回の経験を糧にして、周りの人と協力する大切さを忘れず、よりよい取り組みを目指していきたいと思います。
人文学部社会学科2年次生 清水杏

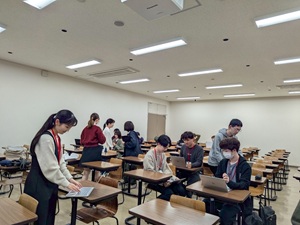
伴走ボランティア
4月20日(日曜日)、えひめアイフレンド伴走クラブの伴走ボランティアに参加させていただきました。
伴走ボランティアは、視覚に障がいのある方がランニングやウォーキングをする際に、その方の目となり、手引きをするなどして安全を確保しながら、コースを案内するというボランティアです。
当日は松山市総合福祉センターに集合し、伴走する際の手順や注意点、手引きの仕方などを教えていただきました。伴走する際は「〇メートル先を〇度右にカーブ」と具体的に表したり、「〇時の方向」と時計の文字盤に例えて伝えたりすることなどを初めて知り驚きました。
次に、実際に伴走をしました。今回は、松山総合福祉センターを出発し、松山城のお堀の周りを回り、松山市総合福祉センターに帰るというルートでした。今回、私は主にランナーと伴走者の前を走り、危険がないかどうかを先に確認するという役割を担当しました。周りの安全の確認をしながら、ランナーに追いつかれないように、かつ離れすぎないように走ることは、一度に考えることが多く大変でしたが楽しかったです。
最後に、少し伴走者の役割をさせていただきました。皆さんは走るペースが速く、私が置いて行かれそうでしたが、「スピードは大丈夫ですか?」と確認しながら一生懸命走りました。
今回初めて伴走をしてみて、伴走中は考える事が多く大変だと感じました。ですが、関わった皆さんが優しく雑談しながら走ってくださったり、わからないことは丁寧に教えてくださったりしたことが、とても嬉しかったです。
人文学部社会学科3年次生 坂本結菜
入学式における情報保障
4月3日(木曜日)、愛媛県県民文化会館で行われた入学式にて、パソコンテイクによる情報保障を行いました。これに先立ち、3月28日(金曜日)、4月1日(火曜日)に大学内で事前準備を行い、4月2日(水曜日)に入学式会場にて前日準備を行いました。
事前準備では、司会原稿等を一つのデータにまとめ、誤字チェックやルビ入れ(ふりがなを振ること)をしたり、スクリーンに映し出した時に読みやすい大きさや文字数となるよう改行を行ったりしました。今年度は式典での情報保障が初めてのメンバーが多くいましたが、経験者を中心に、来年度への引継ぎも行いながら進めていきました。事前準備は作業の関係で当初の予定より1日少ない日数となりましたが、作業を分担し、期間内にすべて終えることができました。
前日と入学式当日には、急遽原稿の変更や追加があったり、当日はパソコンの接続が切れるというトラブルがあったりもしましたが、参加メンバー全員の協力により迅速に対応することができ、大きな失敗もなく無事終えることができ、達成感がありました。また、リアルタイムでタイピングしなければならない場面もありましたが、遅れずミスなく打ち込む2年次生の姿を見て、後輩の成長に感動し、嬉しくなりました。
情報保障を通して新入生の門出をお祝いできたこと、またPOPとしての主要な活動を多くの方にみていただけたことがとても嬉しかったです。POPに入っていなければできなかった、貴重な経験ができました。
法学部3年次生 矢野深鈴
























