株主提案権の適正な運用は株主総会の活性化と企業成長につながる
法学部法学科教授
内海 淳一 UTSUMI Junichi
●略歴
1960 年 福岡市出身
1988 年 福岡大学法学部卒業
1990 年 福岡大学大学院法学研究科博士課程前期修了
1993 年 福岡大学大学院法学研究科博士課程後期満期退学
1994 年 福山平成大学経営学部経営法学科専任講師
2003 年 松山大学法学部助教授
2008 年~2009年 SMU(サザンメソジスト大学)Dedman School of Law客員研究員
2015年~ 2016年 法政大学法学部客員研究員
2019 年 松山大学法学部教授(現在に至る)
形骸化する株主総会の健全化を目的とした制度
株式会社の構成員である株主が、株主総会において議題・議案を提出することができる株主提案権について研究しています。もともと株主総会というものに興味があり、大学院時代、ある先生が株主であった会社の株主総会に代理人として出席させてもらったことが、この研究を始めるきっかけとなりました。当時の株主総会は絵に描いたような〝シャンシャン総会〞で、議論も何もなく、あっという間に終わってしまい「なんだこりゃ!?」と呆気にとられてしまいましたが、それが理由でさらに関心が強くなったようにも思います。
日本では明治時代に最初の株式会社が誕生しています。株式会社の株主は、会社の実質的な所有者ですが、通常は複数いるため、株主総会を開いて意見交換や意思決定を行います。しかし、一般株主の多くは、株式を所有することを投資ではなく投機と捉えていて、キャピタル・ゲイン(売買差益)や配当さえきちんと受け取ることができていれば満足であり、経営に関しては興味・関心がなく、社員株主や総会屋と呼ばれる人たち以外、株主総会に出席する人もごく限られていました。こうした形骸化した株主総会に対し、開かれた対話を促進するべきという声が学界などから上がり、1981(昭和56)年に商法改正が行われ、株主提案権制度が導入されることになったのです。
提案権行使の濫用化に伴い規制を求める声が高まる
株主提案権は、会社法上、一定の要件を備えた株主であれば、株主総会を通じて会社としての意思決定内容に関与することが認められている権限です。特に日本では、その内容を会社の根本規則である定款に記載するよう求める場合、必ず株主総会で決議しなければなりません。1981年の商法改正当時は、総会屋による株主総会の運営妨害、株主と経営者間のコミュニケーション不足、株主による経営チェックやコントロール機能不全などが問題視されていました。ただ、実際の株主提案権行使は、原発反対活動の一環として市民運動型株主に利用されていたくらいで、一般的にはあまり活用されていませんでしたが、コーポレートガバナンスが浸透し始めてきた2000年前後、会社不祥事が頻発したこともあり、「物言う株主」として一般株主も積極的に提案権を行使するようになりました。
ところが、一人の株主が建設的とは言い難い内容の議案を100個も提案するような、濫用的に株主提案権が行使される事態へと発展していきます。その目的は単なる嫌がらせだったり、売名行為であったりと様々ですが、これにより株主総会の健全な運営が著しく阻害されます。思うに、株主提案権の導入当初から、問題のある提案がされるおそれが秘められていました。一人の株主が提案できる数の制限がないため、このような事態も起こるのであり、今では提案個数の制限など、提案権に一定の規制を設けようとする法改正が進んでいます。

株主提案権の濫用的事例 イラスト/浅川 英徳
建設的な対話を促進する規律の構築を模索する
会社法(商法)は、法体制を体系化してルールとした大陸法と、判例を中心に集約してルールとした英米法に大別されますが、日本の場合は、大陸法をベースに英米法的な改正が多くなされています。しかし、株主提案権に関して、アメリカではSEC(証券取引委員会)が株主からの提案をある程度選別することができますが、日本にはそういうルールがなく、比較的簡単に提案することができてしまうのです。
もちろん、株主総会でいい意見を言ってくれる株主もいます。株主が積極的に株主総会に参画し、本気で会社の経営について考えるようになれば議論が活性化し、経営も良い方向へと向かっていくはずです。開かれた株主総会、できるだけ大勢の株主に参加してもらえる株主総会として、ハイブリッド型ヴァーチャル総会を導入するという話も出てきています。また、外国の会社経営者には〝会社は株主のもの〞という意識が強くありますが、日本の経営者の多くは会社を自分たちのものだと考えていて、そのあたりの意識改革も不可欠です。
このように株主提案権の行使により、本来あるべき株主と経営陣との「建設的な対話」を促進するため、日本および諸外国の法律・ルールの運用実態がどうなっているか調査・検証を重ねながら、※ハードローとしての会社法だけではなく、コーポレート・ガバナンス・コードなどの※ソフトローを含めた規律が必要と思われます。
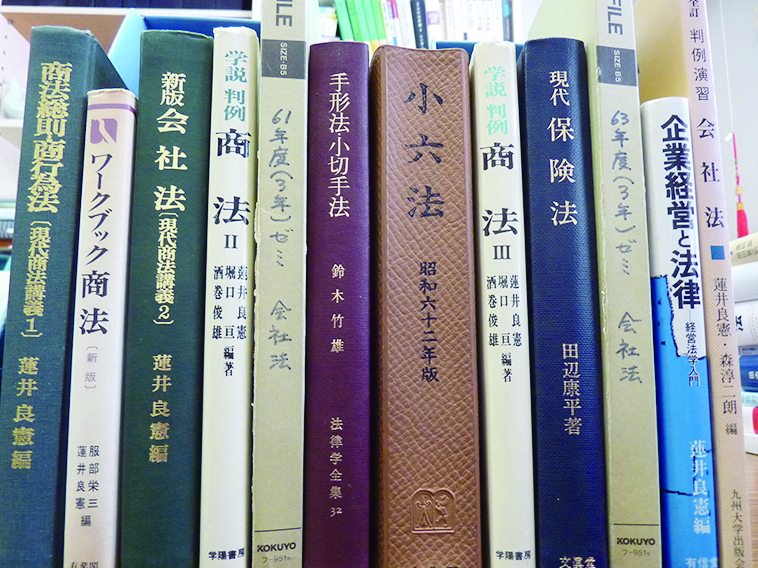
学生時代に使用した商法科目(総則・商行為法、会社法、手形・小切手法、保険法)の教科書・六法等。
この記事は松山大学学園報「CREATION」NO.203でご覧いただけます。





















